生活道路は30km/h制限に?
電動モビリティ時代の新・交通ルール
-300x200.jpeg)
電気自動車や電動バイク、電動の乗り物の種類が急激に増えたため、2026年9月から、道路交通法が一部変更されます。交通ルールは知らなかったでは済まされないため、最新情報をキャッチして頭に入れておくことが大事ですよね!今回は話題になっている日本の交通ルール関連のトピックをご紹介します!知って置いて安心の内容になっていますので、まだ知らない人に教えてあげてください。
「生活道路」の制限速度が一気に30km/hに
来たる2026年9月、いわゆる「生活道路」とされる道路の法定速度が従来の60 km/hから30 km/hに大幅に引き下げられます。
の背景が削除されました-300x200.png)
「生活道路」とは、中央線や中央分離帯が設けられておらず、車道幅員が5.5 m未満など歩行者・自転車との接触リスクが高い道路を指します。
この改定では、速度標識が既に設置されている道路などはその標識が優先されるため、必ずしもすべての該当道路が30 km/hになるわけではありません。改正の背景には、歩行者・自転車が関係する死亡事故の多くが身近な狭い道で起きており、速度低減が致死率を下げる有効性を示している点があります

この速度制限の変更を知らずに従来速度で走行していた場合、30 km/h超過となって即違反となる可能性があるため、特に住宅街などでは速度意識を改める必要があります。
新規「新原付」制度と50ccバイクの新車生産終了
新車としての排気量50cc以下の原動機付バイクが、日本国内で新規生産されなくなります。
これは排ガス規制強化を受けて、50ccクラスのエンジンでは触媒(3元触媒/プラチナ・ロジウム・パラジウムなどを含む)を十分な温度にまで上げて有害ガスを浄化することが難しいためです。
一方で「新原付」と呼ばれる排気量125ccまでのカテゴリーが登場しますが、最高出力4.5 kW以下で速度も30 km/hという仕様となるため、従来の50cc原付と比べて「遅い・大きい・高価格」という印象を持たれる可能性があります。
-300x200.jpeg)
既に所有している50cc原付は継続して利用できますが、新車購入に際しては選択肢が変わることになります。現時点では、新基準の原付は割高になっている傾向が強いので、購入には慎重になっているユーザーが多い様です。他にも、125ccのバイクを伸び伸びと制限を気にせず乗りたいユーザーには、原付2種免許を取る方が効率が良い場合が多いです。
自動車による自転車追い抜きの新ルール
2024年以降の改正案で、自動車が同じ方向に進行する自転車の右側を追い抜く際、「自転車との間に十分な間隔がない場合、安全な速度で走行しなければならない」という新たな義務が課されました。
-300x200.jpeg)
この「十分な間隔」については法令上の具体的数値は明記されておらず、報道などでは目安として1〜1.5 m以上とし、速度差は自転車の平均速度+5〜10 km/h程度という試算があります。
このルール改正により、自転車が隣に走行している際に車が「ビューン」と無警戒に抜いていく行為は、法律上問題になる可能性があります。自転車側も「道路左端へできる限り寄る」という義務が明記される方向です。
自転車への「青切符(反則金)」導入で取り締まり強化
2024年11月1日から施行された改正法律により、運転中のスマートフォン操作や酒気帯び、自転車による信号無視などが「反則金」の対象となる「青切符」制度が自転車にも適用される方向です。
約113項目に及ぶ違反が対象となり、罰金金額は例えば「運転中のスマホ使用」で1万2,000円、「信号無視」で6,000円などと報じられています。
16歳以上の自転車利用者から適用されるとされ、高校生も罰金対象となる可能性があります。この改正が意味するのは、自転車運転が単なる“軽い移動手段”ではなく、車両に近い扱いで法令遵守が求められるという転換です。
これら改正の背景にある「事故防止と死傷軽減」
今回の一連の改正は、事故発生の実態を踏まえたものです。
たとえば、道幅5.5 m未満の道路における歩行者・自転車乗用中の事故死傷率は、幅員5.5 m以上の道路の約1.8倍と報告されています。速度についても、時速30 kmで衝突した場合の致死率は約10%なのに対して、50 kmの場合は80%以上に達するという試算があります。
このように、道路環境や速度が死亡事故の発症率に大きく影響しており、生活道路の速度引き下げや自転車運転の法的強化は「命を守るため」の整備と言えます。
日常にすぐ活かせる「注意すべきポイント」
-300x200.jpeg)
改正内容を理解したうえで、実際に運転・移動する際には以下の点に気を付けてください:
- 住宅街・生活道路とされる道路を走る際、速度標識がない場合は30 km/hの可能性があることを頭に入れ、走行速度をゆとりあるものにする。
- 自転車の横を車で抜く際には、側方間隔を最低1 mを目安に確保し、速度差を抑えて通過する。
- 自転車を運転する際には、スマホ操作・信号無視・並走・傘差し運転などが罰則対象となる可能性があるため、乗車中の行動を今一度見直す。
- 原付バイクの新車購入を考えている場合、50ccクラスが新規生産終了になっている可能性を理解し、「新原付」などの制度変更を確認する。
- 速度標識・通行帯・標示が変わる可能性もあるため、走行前に近隣の案内・表示を確認する習慣を持つ。
以上のように、法令変更は日常の移動の中で影響の大きいものです。安全確保・違反リスク回避のため、今から準備をしておくことが望ましいと言えます。
■他にも最新の記事はこちら↓
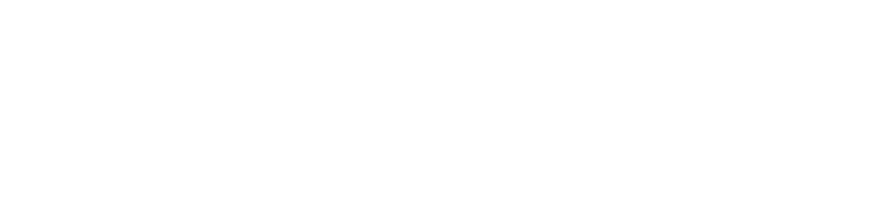
.jpeg)
カテゴリー