『えっ、保険証のかわりにスマホ?』
【iPhoneで診察OKの未来】
スマホで保険証が使える仕組み
明日からは全国の準備が整った医療機関や薬局で本格導入される予定であり、
導入済みかどうかはステッカーで確認できる。
-300x287.jpeg)
しかし、実際の患者への周知はまだ十分でなく
「知らなかった」「スマホを使いこなせないので難しい」といった声も聞かれる。
このスマホ連動サービスはiPhoneやAndroidに搭載されたマイナンバーカードを使って健康保険証として利用できるサービスです。従来は診察時に保険証を提示する必要がありましたが、スマホに登録したマイナンバーカードを提示することで代用できるようになります。
対象となるのは、専用ステッカーが貼られた医療機関で、対応機器が設置されている場所から順次利用が広がります。すでにマイナンバーカードリーダーを導入している病院やクリニックでは、スマホ対応用のリーダーを追加するだけで運用が可能です。そのため、今後も多くの医療機関で導入が進んでいく予定。
利用に対する不安と戸惑い
従来の保険証は提示するだけで済んでいたのに比べ、
スマートフォンにさまざまな情報をまとめることに不安を感じる人もいる様です。
-300x201.jpeg)
「情報を全部スマホに入れるのは怖い」といった声や、「しばらくは使わないと思う」といった慎重な姿勢も見られます。クリニック側からも、患者がスマートフォンと連動させること自体が大きなハードルとされ、受付職員が患者に詳しく説明するのは難しいため、自宅で事前に登録を済ませてから来院する必要があるとの意見もある。
登録に必要な手順
スマホ保険証を利用するには「マイナポータル」からの登録が必要です。
必要なものは以下の通りです。
| 必要書類・資料 | 詳細事項 |
|---|---|
| マイナンバーカード | 必須 |
| 暗証番号 | マイナンバーカード受取時に設定した4桁 (利用者証明用電子証明書のパスワード) |
| 本人確認書類 | マイナンバーカードがない場合: マイナンバーが分かる書類+顔写真付き本人確認書類 |
| マイナポータルアプリ | スマホから登録する場合に必要 |
| 手動パスワード | 英数字6〜16文字 |
| 利用登録端末 | スマホまたは顔認証付きカードリーダー等 |
登録は、役所の窓口や医療機関にある顔認証付きカードリーダー、スマホのマイナポータルアプリ、セブン銀行ATMなどで可能です。初回の利用登録はいずれかの方法で行います。
-300x269.jpeg)
これらを入力してマイナンバーカードを読み取らせることで本人確認が行われ、その後新しい暗証番号を設定します。登録作業はおよそ5分で完了し、パスワードを忘れた場合は専用アプリやコンビニでリセット可能です。準備を済ませればスマホだけで診察が受けられるほか、医療機関にとっても受付業務の効率化になる。
医療機関側での準備と対応
利用には医療機関側に専用の読み取り端末が必要です。
既存のマイナンバーカード対応機器の中には、そのままスマートフォンの読み取りにも対応できる機種があります。それ以外の機器でも、市販のスマホ用リーダーを追加すれば対応可能なため、大掛かりな設備投資やソフトウェア改修は不要です。
-300x200.jpeg)
すでにマイナンバーカードを保険証として読み取っている施設は、短期間で導入が完了し、患者も医療機関側も大きな負担なく利用開始できます。一方で、新しい仕組みに慎重な姿勢を見せる医療機関もあり、顔認証がうまくいかないケースや、スマホ対応によって受付職員の業務が増えることへの懸念が指摘されています。導入を進める上では、業務が過度に複雑化しない工夫が必要。
実際の利用手順
iPhoneでの利用方法は、まず「スマートフォンを利用」を選択、機種をiPhoneに設定します。
マイナンバーカードアプリを起動し、顔認証や暗証番号で本人確認。その後、スマホを読み取りリーダーにかざし、画面が切り替わるまでしっかりと置き続けることで認証が完了します。読み取りの際に一瞬音が鳴っても、画面が変わるまでスマホを離さないことが重要です。すべての内容に同意または個別に同意を選び、「終了」を押すと保険証としての利用が完了します。Androidの場合は手順がほぼ同じですが、電子証明書の暗証番号入力が必須で、その後にリーダーで読み取る流れ。
スマホ保険証の普及を阻む課題
スマホ保険証の普及には依然として課題があります。マイナ保険証自体の利用率は約3割にとどまり、制度の周知や利用促進は十分ではありません。
-300x204.jpeg)
厚生労働省は対応可能な医療機関をホームページで公開する予定ですが、現時点では患者と医療機関双方に運用面での不安が残っています。今後は、利用者にとって分かりやすく、医療現場の負担を増やさない形で制度を定着させていくことが重要です。
生活が便利になるポイント
スマートフォンで保険証を利用できるようになり、
診察券とスマホを持参するだけで受診できる様になります。
-300x300.jpeg)
さらに医療機関によっては、支払いもスマホ一つで完結できる場合もあります。これまでiPhoneのマイナンバーカードは住民票や戸籍関連の証明書取得が主な用途でしたが、現在は本人確認サービスも追加され、契約時の身元確認などにも使えます。加えて、今回の保険証利用が加わることで、スマホ1台でできる手続きが大幅に増え、利便性が向上した。
引き続き対応施設は増えていく模様
現在、電子処方箋などの全面導入については、薬局ではほぼ全ての施設で導入が完了見込みですが、医療機関全体ではまだ導入率が低く、本格的な全国普及は引き続き推進中です。
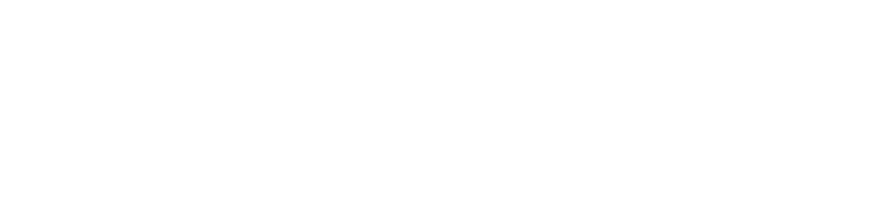
.jpeg)
カテゴリー